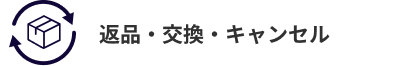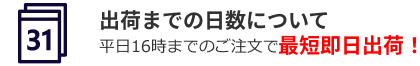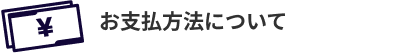電材部品ブログ

キュービクル式高圧受電変電設備とは?種類や用途について解説
工場やオフィスビルなどでは、大量の電力を効率よく使用するために、キュービクル式高圧受電変電設備が設置されています。キュービクル式高圧受電変電設備には、非常に多くの機器が組み込まれていますが、各機器の働きを把握している人はあまり多くありません。 そこで今回は、キュービクル式高圧受電変電設備の概要とともに、設備を構成する内部機器の種類も解説していきます。記事の最後では取り扱いメーカーもご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。 目次 キュービクル式高圧受変電設備とは キュービクル式高圧受変電設備の種類と用途 計器類 開閉器類 保護装置 変圧器 キュービクル式高圧受電変電設備を取り扱う主要メーカー 河村電機産業株式会社 日東工業株式会社 内外電気株式会社 日本電気産業 キュービクル式高圧受変電設備とは キュービクル式高圧受変電設備とは、高圧電力を必要に応じて低圧電力に降圧する設備です。工場や商業施設など、毎日大量の電気を消費する施設では、低圧電力ではなく高圧電力を受電し、自社に設置したキュービクル式高圧受変電設備を通して低電圧に降圧します。 そうすることで、低圧電力を大量に受電するよりも安い単価で電気を使用することが可能です。また、キュービクル式高圧受電変電設備は、過電流やショートを検知すると自動的に電力を遮断する機能を備えているので、電力関連のトラブル防止にも役立ちます。 キュービクル式高圧受変電設備の種類と用途 キュービクル式高圧受電変電設備を構成する内部機器の種類と用途をご紹介します。 計器類 キュービクル式高圧受電変電設備の中には、以下のようにさまざまな計器類が組み込まれています。 種類 概要 電流計 過電流やショートを検出するための機器 電圧計 変圧設備から出力された電圧が正常な範囲に収まっているか確認するための機器 変流計 大きな電流を小さな電流に変流するための機器 電力需給用計器...
キュービクル式高圧受電変電設備とは?種類や用途について解説
工場やオフィスビルなどでは、大量の電力を効率よく使用するために、キュービクル式高圧受電変電設備が設置されています。キュービクル式高圧受電変電設備には、非常に多くの機器が組み込まれていますが、各機器の働きを把握している人はあまり多くありません。 そこで今回は、キュービクル式高圧受電変電設備の概要とともに、設備を構成する内部機器の種類も解説していきます。記事の最後では取り扱いメーカーもご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。 目次 キュービクル式高圧受変電設備とは キュービクル式高圧受変電設備の種類と用途 計器類 開閉器類 保護装置 変圧器 キュービクル式高圧受電変電設備を取り扱う主要メーカー 河村電機産業株式会社 日東工業株式会社 内外電気株式会社 日本電気産業 キュービクル式高圧受変電設備とは キュービクル式高圧受変電設備とは、高圧電力を必要に応じて低圧電力に降圧する設備です。工場や商業施設など、毎日大量の電気を消費する施設では、低圧電力ではなく高圧電力を受電し、自社に設置したキュービクル式高圧受変電設備を通して低電圧に降圧します。 そうすることで、低圧電力を大量に受電するよりも安い単価で電気を使用することが可能です。また、キュービクル式高圧受電変電設備は、過電流やショートを検知すると自動的に電力を遮断する機能を備えているので、電力関連のトラブル防止にも役立ちます。 キュービクル式高圧受変電設備の種類と用途 キュービクル式高圧受電変電設備を構成する内部機器の種類と用途をご紹介します。 計器類 キュービクル式高圧受電変電設備の中には、以下のようにさまざまな計器類が組み込まれています。 種類 概要 電流計 過電流やショートを検出するための機器 電圧計 変圧設備から出力された電圧が正常な範囲に収まっているか確認するための機器 変流計 大きな電流を小さな電流に変流するための機器 電力需給用計器...

冷媒用被覆管とは?種類や用途について解説
エアコンを設置する際には、室内機と室外機を接続するために冷媒用被覆管を使用します。ただし、冷媒用被覆管には複数の種類があり、使用できる場面もタイプごとに決められているので、それぞれの違いを把握しておかなければなりません。 そこで今回は、冷媒用被覆管の種類を用途とともに解説します。記事の後半では、冷媒用被覆管を取り扱うメーカーもご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。 目次 冷媒用被覆管とは 冷媒用被覆管の種類と用途 シングルコイル(2ブ3ブ) ペアコイル(2ブ3ブ・3ブ5ブ) 冷媒用被覆管を取り扱う主要メーカー フローバル 因幡電機産業 オーケー器材株式会社 パナソニック 桃陽電線株式会社 冷媒用被覆管とは 冷媒用被覆管とは、冷媒配管の表面を断熱材で覆った空調用の資材です。エアコンの室外機と室内機の間をつなぎ、冷媒を循環させる目的で使用されます。 配管がむき出しになっていると結露を起こすので、冷媒配管の外側はポリエチレンフォームなどの断熱材で覆われています。なお、冷媒用被覆管は直射日光や雨風にさらされると劣化してしまうため、配管化粧カバー内に収納しなくてはなりません。 冷媒用被覆管の種類と用途 この項目では、冷媒用被覆管の種類を用途とともにご紹介していきます。 シングルコイル(2ブ3ブ) 冷媒用被覆管のシングルコイル(2ブ3ブ)とは、 単一の銅管に断熱材が巻かれているものです。銅管の口径が6.35mmのものを2分(2ブ)、配管の口径が9.52mmのものを3分(3ブ)と呼びます。 シングルコイルは、配管がシンプルで取り扱いやすい点がメリットです。そのため、小規模なエアコンや特定の配管が必要な場合に使用されるケースが多いです。ただし、複数の配管が必要なエアコンや電気出力量の大きいエアコンなどでは、シングルコイルだと施工時に手間がかかるため、ペアコイルの利用が推奨されています。 ペアコイル(2ブ3ブ・3ブ5ブ) 冷媒用被覆管のペアコイル(2ブ3ブ・3ブ5ブ)とは、2本の銅管に断熱材が巻かれている配管で、大小の2本がセットになっています。配管口径が6.35mmのものが2分(2ブ)、9.52mmのものが3分(3ブ)、15.88mmのものが5分(5ブ)に分類されるので、2ブ3ブは、6.35mm×9.52mm、3ブ5ブは、9.52mm×15.88mmです。 ペアコイルを接続するためには、銅管の端をラッパ上に広げるフレア加工を施す必要があります。フレア加工を丁寧に施さなければ、配管のつなぎ目から冷媒ガスが漏れてしまうため注意しましょう。 冷媒用被覆管を取り扱う主要メーカー この項目では、冷媒用被覆管を取り扱う主要メーカーをご紹介します。 フローバル フローバルは、2014年からエアコン部材の開発・販売を実施しているメーカーです。シングルコイルとペアコイルの両方を取り扱っていますが、いずれも自社開発のOEM生産なので、コストパフォーマンスに優れている点が大きな特徴といえます。...
冷媒用被覆管とは?種類や用途について解説
エアコンを設置する際には、室内機と室外機を接続するために冷媒用被覆管を使用します。ただし、冷媒用被覆管には複数の種類があり、使用できる場面もタイプごとに決められているので、それぞれの違いを把握しておかなければなりません。 そこで今回は、冷媒用被覆管の種類を用途とともに解説します。記事の後半では、冷媒用被覆管を取り扱うメーカーもご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。 目次 冷媒用被覆管とは 冷媒用被覆管の種類と用途 シングルコイル(2ブ3ブ) ペアコイル(2ブ3ブ・3ブ5ブ) 冷媒用被覆管を取り扱う主要メーカー フローバル 因幡電機産業 オーケー器材株式会社 パナソニック 桃陽電線株式会社 冷媒用被覆管とは 冷媒用被覆管とは、冷媒配管の表面を断熱材で覆った空調用の資材です。エアコンの室外機と室内機の間をつなぎ、冷媒を循環させる目的で使用されます。 配管がむき出しになっていると結露を起こすので、冷媒配管の外側はポリエチレンフォームなどの断熱材で覆われています。なお、冷媒用被覆管は直射日光や雨風にさらされると劣化してしまうため、配管化粧カバー内に収納しなくてはなりません。 冷媒用被覆管の種類と用途 この項目では、冷媒用被覆管の種類を用途とともにご紹介していきます。 シングルコイル(2ブ3ブ) 冷媒用被覆管のシングルコイル(2ブ3ブ)とは、 単一の銅管に断熱材が巻かれているものです。銅管の口径が6.35mmのものを2分(2ブ)、配管の口径が9.52mmのものを3分(3ブ)と呼びます。 シングルコイルは、配管がシンプルで取り扱いやすい点がメリットです。そのため、小規模なエアコンや特定の配管が必要な場合に使用されるケースが多いです。ただし、複数の配管が必要なエアコンや電気出力量の大きいエアコンなどでは、シングルコイルだと施工時に手間がかかるため、ペアコイルの利用が推奨されています。 ペアコイル(2ブ3ブ・3ブ5ブ) 冷媒用被覆管のペアコイル(2ブ3ブ・3ブ5ブ)とは、2本の銅管に断熱材が巻かれている配管で、大小の2本がセットになっています。配管口径が6.35mmのものが2分(2ブ)、9.52mmのものが3分(3ブ)、15.88mmのものが5分(5ブ)に分類されるので、2ブ3ブは、6.35mm×9.52mm、3ブ5ブは、9.52mm×15.88mmです。 ペアコイルを接続するためには、銅管の端をラッパ上に広げるフレア加工を施す必要があります。フレア加工を丁寧に施さなければ、配管のつなぎ目から冷媒ガスが漏れてしまうため注意しましょう。 冷媒用被覆管を取り扱う主要メーカー この項目では、冷媒用被覆管を取り扱う主要メーカーをご紹介します。 フローバル フローバルは、2014年からエアコン部材の開発・販売を実施しているメーカーです。シングルコイルとペアコイルの両方を取り扱っていますが、いずれも自社開発のOEM生産なので、コストパフォーマンスに優れている点が大きな特徴といえます。...

インターホン用の配線・コンセントとは?
インターホンを設置するためには、通信線やVVFケーブルといった配線、および宅内コンセントが必要です。ただし、配線の必要本数や宅内コンセントの使用有無は、設置するインターホンによって異なります。 そこで今回はインターホン用の配線やコンセントの概要、選び方、交換時期の目安、および主要なインターホンの種類や取り扱いメーカーなどをご紹介していきます。 目次 インターホン用の配線・コンセントとは インターホン用の配線・コンセントを使用する機器の種類・用途 住宅用ドアホン マンション用 インターホン用の配線・コンセントの交換時期の目安 インターホン用の配線・コンセントの選び方・比較ポイント インターホン用の配線・コンセントを使用した機器を扱う主なメーカー インターホン用の配線・コンセントとは インターホン用の配線は、通信線とVVFケーブルの2種類です。通信線はインターホンのチャイム側に使用する配線で、チャイムや音声、映像などを親機に伝える役割を持ちます。一方のVVFケーブルは、インターホンの親機に電源を供給するために使用される配線です。 また、インターホンの親機には、コンセントタイプもあります。コンセントタイプの親機は、自宅のコンセントにアダプターを設置するだけで利用を開始できます。 インターホン用の配線・コンセントを使用する機器の種類・用途 ここでは、インターホン用の配線とコンセントを使用する機器の種類を、用途とともにご紹介します。 住宅用ドアホン 住宅用ドアホンとは、一般住宅に設置されるタイプのインターホンです。呼び出し機能と通話機能付きが基本ですが、ワイヤレス子機と連動しているタイプや、録画機能が付いているタイプ、防犯・防災の各種センサーと連動しているタイプなど、さまざまな種類があります。 新築に設置する住宅用ドアホンは、配線工事タイプが主流です。ただし、古い住宅で配線工事が難しい場合でも、コンセントタイプの親機や乾電池式のチャイムを選択すると、最新式の住宅用ドアホンに付け替えられます。 マンション用 マンション用インターホンは、マンションに設置されるインターホンです。マンション用のインターホンも住宅用ドアホンと同じく、録画機能やモニター付き、ワイヤレス子機付きなど複数の種類があります。ただし、マンション用はエントランスのオートロックを解錠できる機能が付いている点が、住宅用ドアホンとの大きな違いです。 また、マンション用には暗い廊下でも顔をはっきり映し出す暗視機能、広範囲を映し出して不審者対策に役立つワイドビュー機能が付いているタイプもあります。 インターホン用の配線・コンセントの交換時期の目安 インターホンの配線やコンセントの交換時期は、10年~15年が目安とされています。とくに、設置から10年を越えると経年劣化による故障を起こす確率が高まるので、十分に注意しましょう。 インターホンの配線やコンセントを交換せずに使い続けると、音声が聞こえなかったり映像が映らなくなったりするほか、チャイムが勝手に鳴ったり、音声に雑音が混ざったりなどの不具合が起こってしまう可能性があります。 インターホンが正常に機能しないと、来客に気付かず不便な生活を送ることになってしまいます。そのため、設置から10年以上経過している場合は、一度業者に点検を依頼すると良いでしょう。 インターホン用の配線・コンセントの選び方・比較ポイント インターホン用の配線やコンセントの選び方は、設置するインターホンによって変わります。ワイヤレスインターホンは配線工事なしで使用できるインターホンなので、配線を選ぶ必要はありません。ただし、コンセントタイプの親機を選んだ場合は、宅内のコンセントから電源を取得する必要があります。 電池式インターホン・電源コード式インターホンは、チャイムに2本の通信線が必要です。ワイヤレスインターホンと同じように、親機は宅内のコンセントから電源を取得します。 電源直結式インターホンは、通信線が2本、親機の電源供給用のVVFケーブルが2本必要なインターホンです。電源直結式インターホンは、親機の電源を宅内コンセントから取得しないので、設置するためには配線工事が必要です。 インターホン用の配線・コンセントを使用した機器を扱う主なメーカー...
インターホン用の配線・コンセントとは?
インターホンを設置するためには、通信線やVVFケーブルといった配線、および宅内コンセントが必要です。ただし、配線の必要本数や宅内コンセントの使用有無は、設置するインターホンによって異なります。 そこで今回はインターホン用の配線やコンセントの概要、選び方、交換時期の目安、および主要なインターホンの種類や取り扱いメーカーなどをご紹介していきます。 目次 インターホン用の配線・コンセントとは インターホン用の配線・コンセントを使用する機器の種類・用途 住宅用ドアホン マンション用 インターホン用の配線・コンセントの交換時期の目安 インターホン用の配線・コンセントの選び方・比較ポイント インターホン用の配線・コンセントを使用した機器を扱う主なメーカー インターホン用の配線・コンセントとは インターホン用の配線は、通信線とVVFケーブルの2種類です。通信線はインターホンのチャイム側に使用する配線で、チャイムや音声、映像などを親機に伝える役割を持ちます。一方のVVFケーブルは、インターホンの親機に電源を供給するために使用される配線です。 また、インターホンの親機には、コンセントタイプもあります。コンセントタイプの親機は、自宅のコンセントにアダプターを設置するだけで利用を開始できます。 インターホン用の配線・コンセントを使用する機器の種類・用途 ここでは、インターホン用の配線とコンセントを使用する機器の種類を、用途とともにご紹介します。 住宅用ドアホン 住宅用ドアホンとは、一般住宅に設置されるタイプのインターホンです。呼び出し機能と通話機能付きが基本ですが、ワイヤレス子機と連動しているタイプや、録画機能が付いているタイプ、防犯・防災の各種センサーと連動しているタイプなど、さまざまな種類があります。 新築に設置する住宅用ドアホンは、配線工事タイプが主流です。ただし、古い住宅で配線工事が難しい場合でも、コンセントタイプの親機や乾電池式のチャイムを選択すると、最新式の住宅用ドアホンに付け替えられます。 マンション用 マンション用インターホンは、マンションに設置されるインターホンです。マンション用のインターホンも住宅用ドアホンと同じく、録画機能やモニター付き、ワイヤレス子機付きなど複数の種類があります。ただし、マンション用はエントランスのオートロックを解錠できる機能が付いている点が、住宅用ドアホンとの大きな違いです。 また、マンション用には暗い廊下でも顔をはっきり映し出す暗視機能、広範囲を映し出して不審者対策に役立つワイドビュー機能が付いているタイプもあります。 インターホン用の配線・コンセントの交換時期の目安 インターホンの配線やコンセントの交換時期は、10年~15年が目安とされています。とくに、設置から10年を越えると経年劣化による故障を起こす確率が高まるので、十分に注意しましょう。 インターホンの配線やコンセントを交換せずに使い続けると、音声が聞こえなかったり映像が映らなくなったりするほか、チャイムが勝手に鳴ったり、音声に雑音が混ざったりなどの不具合が起こってしまう可能性があります。 インターホンが正常に機能しないと、来客に気付かず不便な生活を送ることになってしまいます。そのため、設置から10年以上経過している場合は、一度業者に点検を依頼すると良いでしょう。 インターホン用の配線・コンセントの選び方・比較ポイント インターホン用の配線やコンセントの選び方は、設置するインターホンによって変わります。ワイヤレスインターホンは配線工事なしで使用できるインターホンなので、配線を選ぶ必要はありません。ただし、コンセントタイプの親機を選んだ場合は、宅内のコンセントから電源を取得する必要があります。 電池式インターホン・電源コード式インターホンは、チャイムに2本の通信線が必要です。ワイヤレスインターホンと同じように、親機は宅内のコンセントから電源を取得します。 電源直結式インターホンは、通信線が2本、親機の電源供給用のVVFケーブルが2本必要なインターホンです。電源直結式インターホンは、親機の電源を宅内コンセントから取得しないので、設置するためには配線工事が必要です。 インターホン用の配線・コンセントを使用した機器を扱う主なメーカー...

EV充電とは?種類や比較ポイントを紹介
EV(電気自動車)を充電する機器には、複数の種類があります。ただし、充電機器の違いを細かく把握している方はあまり多くありません。 そこで本記事では、EV充電の基本から、EV充電で使用する機器の種類や選び方などを解説します。EVを所有している方や、EVの購入を検討している方、およびEV充電器の設置を検討している企業の方は、ぜひ本記事を参考に最適な充電機器は何か調べてみてください。 目次 EV充電とは EV充電の種類・用途 住宅向けEV PHEV充電用コンセント 普通充電 急速充電 EV充電の種類・用途 住宅向けEV PHEV充電用コンセント EV充電の選び方・比較ポイント LEDベースライトを扱う主なメーカー EV充電とは EV充電とは、EV(電気自動車)に充電することです。一般的な自動車はエネルギーとしてガソリンを注入しますが、EVのエネルギーは電気なので、スマホと同じように充電が切れると動きません。そのため、自動車の運転前に必ず充電する必要があります。 EV充電には「普通充電」と「急速充電」の2種類があり、それぞれ設備を設置するシーンが異なります。また、設置場所も「住宅用」と「パブリック(店舗)用」の2種類あるのが特徴です。 EV充電の種類・用途 この項目では、EV充電の種類や用途を解説していきます。 住宅向けEV 住宅向けEVとは、一般家庭用のEV(電気自動車)です。住宅向けEVを充電する際は、自宅に備え付けられている一般的な屋外用コンセントを使用します。 住宅向けEVは、駐車場に車を停めている間にエネルギーを充電できるので、帰宅するたびに充電する習慣を付けておけば、エネルギー切れに悩む心配はありません。また、住宅向けEVはガソリン車よりエネルギーの充填料金を安く抑えられる点も特徴です。 PHEV充電用コンセント PHEV充電用コンセントとは、PHEV(プラグインハイブリッド車)に充電するための専用コンセントです。PHEV充電用コンセントには、100V・200Vの2種類がありますが、100Vでは出力が弱く充電に時間がかかってしまうので、200Vがメインで採用されています。 ただし、200VのPHEV充電用コンセントを設置するためには、自宅に200Vの電気が通っていなければなりません。築20年以上の住宅には200Vの電気が通っていないケースが多いため、その際はPHEV充電用コンセントを設置する前に200V化するための電気工事が必要です。 普通充電 普通充電とは、戸建て住宅や商業施設、屋外駐車場などに設置されているEV充電設備のひとつです。普通充電では単相100Vまたは200Vコンセントを使用し、10km走行分のエネルギーを100Vだと1時間、200Vだと30分で充電できます。 充電設備のタイプはコンセントが一般的ですが、マンションやビル、屋外駐車場などではボール型の充電設備が設置されているケースもあります。なお、コンセントタイプの普通充電設置を自宅に設置する場合は、数千円で施工可能です。 急速充電 急速充電もEV充電設備のひとつで、電源は3相200Vを使用します。急速充電には中容量タイプと大容量タイプがあり、中容量タイプは80%まで充電するのに30分~1時間、大容量タイプなら15~30分程度で完了します。...
EV充電とは?種類や比較ポイントを紹介
EV(電気自動車)を充電する機器には、複数の種類があります。ただし、充電機器の違いを細かく把握している方はあまり多くありません。 そこで本記事では、EV充電の基本から、EV充電で使用する機器の種類や選び方などを解説します。EVを所有している方や、EVの購入を検討している方、およびEV充電器の設置を検討している企業の方は、ぜひ本記事を参考に最適な充電機器は何か調べてみてください。 目次 EV充電とは EV充電の種類・用途 住宅向けEV PHEV充電用コンセント 普通充電 急速充電 EV充電の種類・用途 住宅向けEV PHEV充電用コンセント EV充電の選び方・比較ポイント LEDベースライトを扱う主なメーカー EV充電とは EV充電とは、EV(電気自動車)に充電することです。一般的な自動車はエネルギーとしてガソリンを注入しますが、EVのエネルギーは電気なので、スマホと同じように充電が切れると動きません。そのため、自動車の運転前に必ず充電する必要があります。 EV充電には「普通充電」と「急速充電」の2種類があり、それぞれ設備を設置するシーンが異なります。また、設置場所も「住宅用」と「パブリック(店舗)用」の2種類あるのが特徴です。 EV充電の種類・用途 この項目では、EV充電の種類や用途を解説していきます。 住宅向けEV 住宅向けEVとは、一般家庭用のEV(電気自動車)です。住宅向けEVを充電する際は、自宅に備え付けられている一般的な屋外用コンセントを使用します。 住宅向けEVは、駐車場に車を停めている間にエネルギーを充電できるので、帰宅するたびに充電する習慣を付けておけば、エネルギー切れに悩む心配はありません。また、住宅向けEVはガソリン車よりエネルギーの充填料金を安く抑えられる点も特徴です。 PHEV充電用コンセント PHEV充電用コンセントとは、PHEV(プラグインハイブリッド車)に充電するための専用コンセントです。PHEV充電用コンセントには、100V・200Vの2種類がありますが、100Vでは出力が弱く充電に時間がかかってしまうので、200Vがメインで採用されています。 ただし、200VのPHEV充電用コンセントを設置するためには、自宅に200Vの電気が通っていなければなりません。築20年以上の住宅には200Vの電気が通っていないケースが多いため、その際はPHEV充電用コンセントを設置する前に200V化するための電気工事が必要です。 普通充電 普通充電とは、戸建て住宅や商業施設、屋外駐車場などに設置されているEV充電設備のひとつです。普通充電では単相100Vまたは200Vコンセントを使用し、10km走行分のエネルギーを100Vだと1時間、200Vだと30分で充電できます。 充電設備のタイプはコンセントが一般的ですが、マンションやビル、屋外駐車場などではボール型の充電設備が設置されているケースもあります。なお、コンセントタイプの普通充電設置を自宅に設置する場合は、数千円で施工可能です。 急速充電 急速充電もEV充電設備のひとつで、電源は3相200Vを使用します。急速充電には中容量タイプと大容量タイプがあり、中容量タイプは80%まで充電するのに30分~1時間、大容量タイプなら15~30分程度で完了します。...

TVアンテナ用の配線・コンセントとは?種類や比較ポイントを紹介
TVアンテナ用の配線・コンセントとは、TVアンテナとテレビを接続するための配信、およびテレビコンセント端子を指します。テレビを視聴するためには、設置場所や視聴目的などに合わせ、適切なTVアンテナや周辺装置を設置しなくてはなりません。 そこで今回は、TVアンテナや周辺装置の種類を用途とともに解説していきます。記事内ではTVアンテナの交換目安や選び方、TVアンテナを取り扱う主なメーカーもご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。 目次 TVアンテナとは TVアンテナの種類・用途 UHFアンテナ BS110°CSアンテナ ミキサー ブースター 分配機 分岐器 分波器 TVアンテナの交換時期の目安 TVアンテナの選び方・比較ポイント TVアンテナを扱う主なメーカー TVアンテナとは TVアンテナとは、電波塔から送信されているテレビ電波を受信するための装置です。TVアンテナを自宅に設置することで、宅内へ設置したテレビに映像が映し出されます。 TVアンテナは大きく分けると、「地デジアンテナ」と「BS/CSアンテナ」の2種類です。ただし、BSやCSを受信するためには、アンテナだけでなく、専用のアンテナケーブルやチューナー内蔵テレビも必要です。 TVアンテナの種類・用途 この項目では、TVアンテナの種類を用途とあわせてご紹介します。 UHFアンテナ UHFアンテナとは、周波数300MHz~3GHzまでの極超短波を受信するアンテナです。主に、地デジ放送や無得LAN、携帯電話の通信に利用されます。 UHFアンテナの種類は、魚の骨のような形状をした「八木式アンテナ」、コンパクトな箱型でデザイン性に優れている「デザインアンテナ」、室内に設置できる「室内アンテナ」の3種類です。受信能力を重視するなら八木式アンテナ、デザイン性を重視するならデザインアンテナ、設置工事をしたくないなら室内アンテナをおすすめします。 BS110°CSアンテナ BS110°CSアンテナとは、衛星放送を受信するためのアンテナです。パラボラアンテナと呼ばれる丸い形状をしており、衛星からの電波を反射鏡で反射させ、一時放射器とコンバーターに集めたあと、周波数を1~3GHzに増幅させます。 BS110°CS放送を見るためには、テレビも衛星放送に対応したものを用意しなければなりません。また、新4K・8K衛星放送を見たい場合も、別途で対応チューナーを内蔵したテレビが必要です。 ミキサー ミキサーとは、地上デジタル放送と、BS/CS放送などの異なる電波をひとつにまとめる装置です。地デジやBS・CS放送を視聴するためには、複数のアンテナケーブルをテレビまで伸ばさなければなりません。 ミキサーがあると、地デジ・BS・CSを切り替えながら1台のテレビで視聴できるようになるので、テレビ周りの配線をスッキリさせられます。ただし、ミキサーは地デジとBS/CSで2つのアンテナを所有している場合に使用する装置なので、地デジのみを視聴する場合は必要ありません。 ブースター...
TVアンテナ用の配線・コンセントとは?種類や比較ポイントを紹介
TVアンテナ用の配線・コンセントとは、TVアンテナとテレビを接続するための配信、およびテレビコンセント端子を指します。テレビを視聴するためには、設置場所や視聴目的などに合わせ、適切なTVアンテナや周辺装置を設置しなくてはなりません。 そこで今回は、TVアンテナや周辺装置の種類を用途とともに解説していきます。記事内ではTVアンテナの交換目安や選び方、TVアンテナを取り扱う主なメーカーもご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。 目次 TVアンテナとは TVアンテナの種類・用途 UHFアンテナ BS110°CSアンテナ ミキサー ブースター 分配機 分岐器 分波器 TVアンテナの交換時期の目安 TVアンテナの選び方・比較ポイント TVアンテナを扱う主なメーカー TVアンテナとは TVアンテナとは、電波塔から送信されているテレビ電波を受信するための装置です。TVアンテナを自宅に設置することで、宅内へ設置したテレビに映像が映し出されます。 TVアンテナは大きく分けると、「地デジアンテナ」と「BS/CSアンテナ」の2種類です。ただし、BSやCSを受信するためには、アンテナだけでなく、専用のアンテナケーブルやチューナー内蔵テレビも必要です。 TVアンテナの種類・用途 この項目では、TVアンテナの種類を用途とあわせてご紹介します。 UHFアンテナ UHFアンテナとは、周波数300MHz~3GHzまでの極超短波を受信するアンテナです。主に、地デジ放送や無得LAN、携帯電話の通信に利用されます。 UHFアンテナの種類は、魚の骨のような形状をした「八木式アンテナ」、コンパクトな箱型でデザイン性に優れている「デザインアンテナ」、室内に設置できる「室内アンテナ」の3種類です。受信能力を重視するなら八木式アンテナ、デザイン性を重視するならデザインアンテナ、設置工事をしたくないなら室内アンテナをおすすめします。 BS110°CSアンテナ BS110°CSアンテナとは、衛星放送を受信するためのアンテナです。パラボラアンテナと呼ばれる丸い形状をしており、衛星からの電波を反射鏡で反射させ、一時放射器とコンバーターに集めたあと、周波数を1~3GHzに増幅させます。 BS110°CS放送を見るためには、テレビも衛星放送に対応したものを用意しなければなりません。また、新4K・8K衛星放送を見たい場合も、別途で対応チューナーを内蔵したテレビが必要です。 ミキサー ミキサーとは、地上デジタル放送と、BS/CS放送などの異なる電波をひとつにまとめる装置です。地デジやBS・CS放送を視聴するためには、複数のアンテナケーブルをテレビまで伸ばさなければなりません。 ミキサーがあると、地デジ・BS・CSを切り替えながら1台のテレビで視聴できるようになるので、テレビ周りの配線をスッキリさせられます。ただし、ミキサーは地デジとBS/CSで2つのアンテナを所有している場合に使用する装置なので、地デジのみを視聴する場合は必要ありません。 ブースター...

漏電遮断器とは?種類や比較ポイントを紹介
漏電遮断器は、感電事故を防ぐための重要機器です。工場だけでなく、一般住宅や自動販売機、スーパーの冷凍ショーケースなど、わたしたちの身近な場所でも活用されています。 ただし、漏電遮断器には複数の種類があり、それぞれ取り付けられる場所も決まっているので、選び方には注意が必要です。 そこで今回は、漏電遮断器の概要や種類、用途などを解説していきます。交換時期の目安や取り扱いメーカーも解説しているため、ぜひ参考にしてください。 目次 漏電遮断器とは 漏電遮断器の種類・用途 高感度形 中感度形 低感度形 漏電遮断器の交換時期の目安 漏電遮断器の選び方・比較ポイント 漏電遮断器を扱う主なメーカー 漏電遮断器とは 漏電遮断器とは、漏電による感電事故や火災を未然に防ぐために設置する機械です。感電事故や火災の危険を検知すると、自動的に電気回路を遮断します。別名は、漏電ブレーカーです。 漏電遮断器は、機器の内部に零相変流器が組み込まれており、回路を往復する電流値を常に測定しています。電気回路に問題が無ければ、行きと帰りの電流値は同じなので異常は発生しません。しかし、行きと帰りの電流値に差が出たときは、どこかで異常が発生していると判断し、電気回路を遮断します。 漏電遮断器の種類・用途 この項目では、漏電遮断器の種類を用途とともにご紹介していきます。 高感度形 高感度形は、5~30mAの電流を感知できる漏電遮断器です。高感度形には以下のように3つの区分があり、それぞれ特徴が異なります。 種類 概要 高速形 動作時間0.1秒以内。漏電を感知すると、すぐに回路を遮断するため安全度が高い。ただし、主な分電盤に設置すると漏電が発生した直後にすべての配線が停電する。 時延形 動作時間0.1~2秒以内。上位遮断器を順番に時延することで、広範囲の漏電を防止しつつ、大規模な停電被害を防ぐ。 反限時形 動作時間0.3秒以内。感電事故防止目的で設置するため、危険度の低い漏電には反応しない場合がある。 中感度形 中感度形は、50~1,000mAの電流を感知できる漏電遮断器です。中感度形には以下のように2つの区分があり、それぞれ特徴が異なります。 種類...
漏電遮断器とは?種類や比較ポイントを紹介
漏電遮断器は、感電事故を防ぐための重要機器です。工場だけでなく、一般住宅や自動販売機、スーパーの冷凍ショーケースなど、わたしたちの身近な場所でも活用されています。 ただし、漏電遮断器には複数の種類があり、それぞれ取り付けられる場所も決まっているので、選び方には注意が必要です。 そこで今回は、漏電遮断器の概要や種類、用途などを解説していきます。交換時期の目安や取り扱いメーカーも解説しているため、ぜひ参考にしてください。 目次 漏電遮断器とは 漏電遮断器の種類・用途 高感度形 中感度形 低感度形 漏電遮断器の交換時期の目安 漏電遮断器の選び方・比較ポイント 漏電遮断器を扱う主なメーカー 漏電遮断器とは 漏電遮断器とは、漏電による感電事故や火災を未然に防ぐために設置する機械です。感電事故や火災の危険を検知すると、自動的に電気回路を遮断します。別名は、漏電ブレーカーです。 漏電遮断器は、機器の内部に零相変流器が組み込まれており、回路を往復する電流値を常に測定しています。電気回路に問題が無ければ、行きと帰りの電流値は同じなので異常は発生しません。しかし、行きと帰りの電流値に差が出たときは、どこかで異常が発生していると判断し、電気回路を遮断します。 漏電遮断器の種類・用途 この項目では、漏電遮断器の種類を用途とともにご紹介していきます。 高感度形 高感度形は、5~30mAの電流を感知できる漏電遮断器です。高感度形には以下のように3つの区分があり、それぞれ特徴が異なります。 種類 概要 高速形 動作時間0.1秒以内。漏電を感知すると、すぐに回路を遮断するため安全度が高い。ただし、主な分電盤に設置すると漏電が発生した直後にすべての配線が停電する。 時延形 動作時間0.1~2秒以内。上位遮断器を順番に時延することで、広範囲の漏電を防止しつつ、大規模な停電被害を防ぐ。 反限時形 動作時間0.3秒以内。感電事故防止目的で設置するため、危険度の低い漏電には反応しない場合がある。 中感度形 中感度形は、50~1,000mAの電流を感知できる漏電遮断器です。中感度形には以下のように2つの区分があり、それぞれ特徴が異なります。 種類...