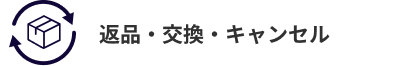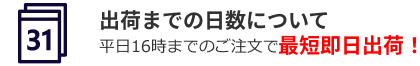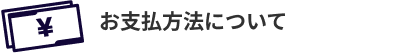電材部品ブログ

ウオルボックスとは?種類や比較ポイントを紹介
ウオルボックスとは、屋内や屋外で電気機器や電子機器を収納するためのボックスです。ウオルボックスを使用すると機器をホコリや雨水などから防護できるため、故障やショートなどのリスクを軽減できます。ただし、ウオルボックスにはいくつか種類があるので、施工前にはそれぞれの違いを把握しておかなければなりません。そこで今回は、ウオルボックスの種類や用途について解説します。記事後半では、交換の目安や選び方なども解説するので、ぜひ参考にしてみてください。 目次 ウオルボックスとは ウオルボックスの種類・用途 タテ型 ヨコ型 屋根付 情報ウオルボックス ウオルボックスの交換時期の目安 ウオルボックスの選び方・比較ポイント ウオルボックスとは ウオルボックスとは、プラスチック製の防雨ボックスです。ボックスの中には電気・電子機器が収納されており、屋内外のさまざまな環境から内部機器を保護します。ウオルボックスは金属製のボックスよりも電波浸透性に優れているので、監視カメラ・無線LANアクセスポイント・ブロードバンド用通信機器などの周辺機器を収納するボックスとして適しています。ちなみに、ウオルボックスは未来工業の商標なので、他社ではプラボックスなど別の名称で呼ばれていますが、製品の形や用途などは同じです。 ウオルボックスの種類・用途 ここでは、ウオルボックスの種類を用途とともに解説します。 タテ型 タテ型とは、タテ方向に長いウオルボックスです。横幅は狭いものの、縦に長さがあるので、縦長のブレーカーや漏電遮断器などを収納できます。タテ型のウオルボックスは左右どちらかの片開きなので、扉1枚を開閉できるスペースがあれば設置可能です。そのため、扉を開くスペースを広く取りにくい場所や、横幅が狭い場所にウオルボックスを設置したい場合は、タテ型が適しています。 ヨコ型 ヨコ型とは、横方向に長いウオルボックスです。タテ型のように縦幅はありませんが、横に長さがあるので、横長の漏電遮断器やブレーカー、コンセントなどの電気機器を収納する際に適しています。ヨコ型のウオルボックスは、タテ型のように片開きタイプもありますが、観音開きタイプや扉が上向きに開くタイプもあります。そのため、前面に扉を開くスペースが取りにくい場合は片開きや上開きタイプ、前面に扉を開くスペースが十分にある場合や、作業スペースを広く取りたい場合は観音開きタイプがおすすめです。 屋根付 屋根付とは、ボックスの上部に小さい屋根が付いているウオルボックスです。ウオルボックスはプラスチック製なので雨に強いですが、屋根が付いているウオルボックスであれば、雨が降っているときに扉を開けて作業をしても雨水が中へ落ちにくいため、より防雨性に優れています。 ウオルボックスはタテ型とヨコ型のどちらも屋根付タイプが販売されているので、より防雨性を高めたい場合は屋根付の利用がおすすめです。 情報ウオルボックス 情報ウオルボックスとは、宅内ハブや、インターネット通信機器などの宅内情報機器を収納するためのボックスです。屋内用と屋外用にわかれているだけでなく、タテ型とヨコ型、どちらのタイプも販売されているため、用途や設置場所に合わせて最適なタイプを選びやすくなっています。また、情報ウオルボックスは、機器の熱がこもらないよう扉の一部がメッシュ加工されているものや、配線位置を自由に決められるよう、ボックスに樹脂製の穴あき基台が取り付けられているものもあります。 ウオルボックスの交換時期の目安 ウオルボックスは防雨性も高く、屋外用であれば耐候性も備えているので、比較的寿命は長いです。しかし、紫外線による変色が起きたり、開閉を重ねたことで扉が完全に閉まらなくなったりしたときは、交換がおすすめです。ウオルボックスを適切な時期で交換しなければ、内部に収納している機器がショートを起こしたり故障をしたりしてしまうので、ウオルボックスは設置後も状態を定期的に確認しましょう。 ウオルボックスの選び方・比較ポイント ウオルボックスは屋内用と屋外用にわかれているので、まずは屋内・屋外のどちらで使用するのかを決めて、使用場所に適したタイプを選びましょう。その後は、ウオルボックスの形状をタテ型またはヨコ型から選びます。ウオルボックスの設置スペースが狭い場合や、ボックス内に入れる機器が縦に長い場合はタテ型がおすすめです。一方、ウオルボックスの設置スペースが広い場合や、ボックス内に入れる機器が横に長い場合はヨコ型を選びましょう。 ただし、ウオルボックス内に宅内情報機器を収納したい場合は、情報ウオルボックスの中から屋内用・屋外用、タテ型・ヨコ型を選んでください。ウオルボックスは、主に以下のメーカーで取り扱っています。 ウオルボックスの取り扱いメーカー パナソニック...
ウオルボックスとは?種類や比較ポイントを紹介
ウオルボックスとは、屋内や屋外で電気機器や電子機器を収納するためのボックスです。ウオルボックスを使用すると機器をホコリや雨水などから防護できるため、故障やショートなどのリスクを軽減できます。ただし、ウオルボックスにはいくつか種類があるので、施工前にはそれぞれの違いを把握しておかなければなりません。そこで今回は、ウオルボックスの種類や用途について解説します。記事後半では、交換の目安や選び方なども解説するので、ぜひ参考にしてみてください。 目次 ウオルボックスとは ウオルボックスの種類・用途 タテ型 ヨコ型 屋根付 情報ウオルボックス ウオルボックスの交換時期の目安 ウオルボックスの選び方・比較ポイント ウオルボックスとは ウオルボックスとは、プラスチック製の防雨ボックスです。ボックスの中には電気・電子機器が収納されており、屋内外のさまざまな環境から内部機器を保護します。ウオルボックスは金属製のボックスよりも電波浸透性に優れているので、監視カメラ・無線LANアクセスポイント・ブロードバンド用通信機器などの周辺機器を収納するボックスとして適しています。ちなみに、ウオルボックスは未来工業の商標なので、他社ではプラボックスなど別の名称で呼ばれていますが、製品の形や用途などは同じです。 ウオルボックスの種類・用途 ここでは、ウオルボックスの種類を用途とともに解説します。 タテ型 タテ型とは、タテ方向に長いウオルボックスです。横幅は狭いものの、縦に長さがあるので、縦長のブレーカーや漏電遮断器などを収納できます。タテ型のウオルボックスは左右どちらかの片開きなので、扉1枚を開閉できるスペースがあれば設置可能です。そのため、扉を開くスペースを広く取りにくい場所や、横幅が狭い場所にウオルボックスを設置したい場合は、タテ型が適しています。 ヨコ型 ヨコ型とは、横方向に長いウオルボックスです。タテ型のように縦幅はありませんが、横に長さがあるので、横長の漏電遮断器やブレーカー、コンセントなどの電気機器を収納する際に適しています。ヨコ型のウオルボックスは、タテ型のように片開きタイプもありますが、観音開きタイプや扉が上向きに開くタイプもあります。そのため、前面に扉を開くスペースが取りにくい場合は片開きや上開きタイプ、前面に扉を開くスペースが十分にある場合や、作業スペースを広く取りたい場合は観音開きタイプがおすすめです。 屋根付 屋根付とは、ボックスの上部に小さい屋根が付いているウオルボックスです。ウオルボックスはプラスチック製なので雨に強いですが、屋根が付いているウオルボックスであれば、雨が降っているときに扉を開けて作業をしても雨水が中へ落ちにくいため、より防雨性に優れています。 ウオルボックスはタテ型とヨコ型のどちらも屋根付タイプが販売されているので、より防雨性を高めたい場合は屋根付の利用がおすすめです。 情報ウオルボックス 情報ウオルボックスとは、宅内ハブや、インターネット通信機器などの宅内情報機器を収納するためのボックスです。屋内用と屋外用にわかれているだけでなく、タテ型とヨコ型、どちらのタイプも販売されているため、用途や設置場所に合わせて最適なタイプを選びやすくなっています。また、情報ウオルボックスは、機器の熱がこもらないよう扉の一部がメッシュ加工されているものや、配線位置を自由に決められるよう、ボックスに樹脂製の穴あき基台が取り付けられているものもあります。 ウオルボックスの交換時期の目安 ウオルボックスは防雨性も高く、屋外用であれば耐候性も備えているので、比較的寿命は長いです。しかし、紫外線による変色が起きたり、開閉を重ねたことで扉が完全に閉まらなくなったりしたときは、交換がおすすめです。ウオルボックスを適切な時期で交換しなければ、内部に収納している機器がショートを起こしたり故障をしたりしてしまうので、ウオルボックスは設置後も状態を定期的に確認しましょう。 ウオルボックスの選び方・比較ポイント ウオルボックスは屋内用と屋外用にわかれているので、まずは屋内・屋外のどちらで使用するのかを決めて、使用場所に適したタイプを選びましょう。その後は、ウオルボックスの形状をタテ型またはヨコ型から選びます。ウオルボックスの設置スペースが狭い場合や、ボックス内に入れる機器が縦に長い場合はタテ型がおすすめです。一方、ウオルボックスの設置スペースが広い場合や、ボックス内に入れる機器が横に長い場合はヨコ型を選びましょう。 ただし、ウオルボックス内に宅内情報機器を収納したい場合は、情報ウオルボックスの中から屋内用・屋外用、タテ型・ヨコ型を選んでください。ウオルボックスは、主に以下のメーカーで取り扱っています。 ウオルボックスの取り扱いメーカー パナソニック...

電線管付属品とは?種類や用途について解説
電線管付属品とは、電線を保護したり配線を整理したりする際に使用する部品です。電線管を施工する際は、電線管付属品を使用することで、より安全に使用できるようになったりメンテナンスがしやすくなったりします。 ただし、電線管付属品にはさまざまな種類があるので、製品ごとに使用すべき場面を把握しておきましょう。 今回は、電線管付属品とは何かといった基本説明から、電線管付属品の種類を用途とともに解説します。 目次 電線管付属品とは 電線管付属品の種類と用途 コネクタ カップリング ノーマルベンド ロックナット 絶縁ブッシング 電線管付属品とは 電線管付属品とは、電線を保護したり配線を整理したりするための部品です。電線管付属品を使用すると、電気設備の安全性や見た目が向上したり、メンテナンスを効率良くおこなえるようになったりします。 電線管付属品にはコネクタやカップリング、ノーマルベンド、ロックナット、絶縁ブッシングなどがあり、電線管の種類や取り付ける目的によって選ぶものが変わります。また、同じ製品であっても取り付ける電線管のサイズによって種類は変わってくるので、電線管付属品を選ぶ際は製品選びに注意をしましょう。 電線管付属品の種類と用途 電線管付属品の種類を、製品の用途とともに解説します。 コネクタ コネクタとは、ボックスや電線管、電気機器を電線保護チューブと接続する際に使用される電線管付属品です。コネクタには主に以下の種類があります。 コネクタの種類 ボックスコネクタ 電線保護チューブとボックスを接続するコネクタ 電気機器用コネクタ 電線保護チューブと電気機器を接続するコネクタ コンビネーションカップリング 電線管保護チューブと電線管を接続するコネクタ 45度ボックスコネクタ 電線保護チューブとボックスを45度の角度で接続するコネクタ 90度ボックスコネクタ 電線保護チューブとボックスを90度の角度で接続するコネクタ コネクタは、電線保護チューブのサイズに合ったものを選びましょう。また、コネクタはボックスや電気機器、電線管と接続するので、取り付け場所の穴径のサイズに合ったものを選ぶことも大切です。...
電線管付属品とは?種類や用途について解説
電線管付属品とは、電線を保護したり配線を整理したりする際に使用する部品です。電線管を施工する際は、電線管付属品を使用することで、より安全に使用できるようになったりメンテナンスがしやすくなったりします。 ただし、電線管付属品にはさまざまな種類があるので、製品ごとに使用すべき場面を把握しておきましょう。 今回は、電線管付属品とは何かといった基本説明から、電線管付属品の種類を用途とともに解説します。 目次 電線管付属品とは 電線管付属品の種類と用途 コネクタ カップリング ノーマルベンド ロックナット 絶縁ブッシング 電線管付属品とは 電線管付属品とは、電線を保護したり配線を整理したりするための部品です。電線管付属品を使用すると、電気設備の安全性や見た目が向上したり、メンテナンスを効率良くおこなえるようになったりします。 電線管付属品にはコネクタやカップリング、ノーマルベンド、ロックナット、絶縁ブッシングなどがあり、電線管の種類や取り付ける目的によって選ぶものが変わります。また、同じ製品であっても取り付ける電線管のサイズによって種類は変わってくるので、電線管付属品を選ぶ際は製品選びに注意をしましょう。 電線管付属品の種類と用途 電線管付属品の種類を、製品の用途とともに解説します。 コネクタ コネクタとは、ボックスや電線管、電気機器を電線保護チューブと接続する際に使用される電線管付属品です。コネクタには主に以下の種類があります。 コネクタの種類 ボックスコネクタ 電線保護チューブとボックスを接続するコネクタ 電気機器用コネクタ 電線保護チューブと電気機器を接続するコネクタ コンビネーションカップリング 電線管保護チューブと電線管を接続するコネクタ 45度ボックスコネクタ 電線保護チューブとボックスを45度の角度で接続するコネクタ 90度ボックスコネクタ 電線保護チューブとボックスを90度の角度で接続するコネクタ コネクタは、電線保護チューブのサイズに合ったものを選びましょう。また、コネクタはボックスや電気機器、電線管と接続するので、取り付け場所の穴径のサイズに合ったものを選ぶことも大切です。...

ケーブルラックとは?種類や用途について解説
ケーブルラックとは、大量のケーブルをまとめて配線する際に使用される配線資材です。ケーブルラックは主に駅のホームや駐車場、公共施設などの壁や天井などで使用されます。 ただし、ケーブルラックは使用場所によって適切なタイプや素材、塗装の仕様などが異なるため、ケーブルラックを使用する際は、それぞれの特徴をあらかじめ把握しておきましょう。 今回は、ケーブルラックの種類や用途、取り扱いメーカーをご紹介します。 目次 ケーブルラックとは ケーブルラックの種類と用途 立上り トレー スーパーダイマ 亜鉛メッキ ケーブルラックとは ケーブルラックとは、大量のケーブルを配線する際に、ケーブルを天井や壁付近でまとめて支える配線資材です。ケーブルにはトレー形やはしご形のタイプがあり、駅のホームや駐車場、公共施設など多くの場所で使用されています。 ケーブルラックは施工場所によって使用できる材質や塗装の仕様が異なるので、仕様別にZMやZAなどの記号が付けられています。そのため、ケーブルラックを施工する際は、タイプだけでなく記号による選定が必要です。 ケーブルラックの種類と用途 ここからは、カップリングの種類を用途とともに解説します。 立上り 立上りとは、上階にケーブルを配線する際に使用されるケーブルラックです。 上階にまたがるようにケーブルを配線する場合、立上りケーブルラックを使用すると、ケーブルが周囲の資材や壁などと摩擦して引っかかるリスクを防止できます。また、立上りケーブルラックを使用するとケーブルが垂れ下がらなくなるので、施工中のつまずき事故も防止可能です。 立上りケーブルラックは片面にケーブルを収納するタイプだけでなく、ラックの両面にケーブルを敷設できる「立上り用両面ラック」もあります。立上り用両面ラックを使用すると、EPS(電気関係の配線を通すために用意された配線スペース)のように限られた場所でも効率よくケーブルを配線できます。 立上りケーブルラックを取り扱っている主なメーカーは、以下のとおりです。 立上りケーブルラックの取り扱いメーカー ネグロス電工 トレー トレーとは底部分が全面板、またはメッシュになっているケーブルラックで、ケーブルを敷設する際は、トレーに空いている穴を使用します。 トレー形のケーブルラックは、はしご形のように底が大きく抜けていないので、下から見上げてもケーブルが見えないことから見栄えの良さを重視したいときに重宝されます。また、ケーブルに触れにくいといったメリットもあるため、露出場所でも安全性を保ちながら設置できる点が特徴です。 ただし、トレー形のケーブルラックの使用場所は、国土交通省が提示する指針によると一般屋内のみに限られています。さらに、はしご形より販売されている製品の種類が少ない点もデメリットです。 トレー形のケーブルラックは、はしご形のようにホコリなどが下へ落ちにくいため、食品工場や飲料工場、製薬工場など、衛生管理が徹底された場所での使用に適しています。 トレー形のケーブルラックを主に取り扱っているメーカーは、以下のとおりです。 トレー形のケーブルラックの取り扱いメーカー ネグロス電工...
ケーブルラックとは?種類や用途について解説
ケーブルラックとは、大量のケーブルをまとめて配線する際に使用される配線資材です。ケーブルラックは主に駅のホームや駐車場、公共施設などの壁や天井などで使用されます。 ただし、ケーブルラックは使用場所によって適切なタイプや素材、塗装の仕様などが異なるため、ケーブルラックを使用する際は、それぞれの特徴をあらかじめ把握しておきましょう。 今回は、ケーブルラックの種類や用途、取り扱いメーカーをご紹介します。 目次 ケーブルラックとは ケーブルラックの種類と用途 立上り トレー スーパーダイマ 亜鉛メッキ ケーブルラックとは ケーブルラックとは、大量のケーブルを配線する際に、ケーブルを天井や壁付近でまとめて支える配線資材です。ケーブルにはトレー形やはしご形のタイプがあり、駅のホームや駐車場、公共施設など多くの場所で使用されています。 ケーブルラックは施工場所によって使用できる材質や塗装の仕様が異なるので、仕様別にZMやZAなどの記号が付けられています。そのため、ケーブルラックを施工する際は、タイプだけでなく記号による選定が必要です。 ケーブルラックの種類と用途 ここからは、カップリングの種類を用途とともに解説します。 立上り 立上りとは、上階にケーブルを配線する際に使用されるケーブルラックです。 上階にまたがるようにケーブルを配線する場合、立上りケーブルラックを使用すると、ケーブルが周囲の資材や壁などと摩擦して引っかかるリスクを防止できます。また、立上りケーブルラックを使用するとケーブルが垂れ下がらなくなるので、施工中のつまずき事故も防止可能です。 立上りケーブルラックは片面にケーブルを収納するタイプだけでなく、ラックの両面にケーブルを敷設できる「立上り用両面ラック」もあります。立上り用両面ラックを使用すると、EPS(電気関係の配線を通すために用意された配線スペース)のように限られた場所でも効率よくケーブルを配線できます。 立上りケーブルラックを取り扱っている主なメーカーは、以下のとおりです。 立上りケーブルラックの取り扱いメーカー ネグロス電工 トレー トレーとは底部分が全面板、またはメッシュになっているケーブルラックで、ケーブルを敷設する際は、トレーに空いている穴を使用します。 トレー形のケーブルラックは、はしご形のように底が大きく抜けていないので、下から見上げてもケーブルが見えないことから見栄えの良さを重視したいときに重宝されます。また、ケーブルに触れにくいといったメリットもあるため、露出場所でも安全性を保ちながら設置できる点が特徴です。 ただし、トレー形のケーブルラックの使用場所は、国土交通省が提示する指針によると一般屋内のみに限られています。さらに、はしご形より販売されている製品の種類が少ない点もデメリットです。 トレー形のケーブルラックは、はしご形のようにホコリなどが下へ落ちにくいため、食品工場や飲料工場、製薬工場など、衛生管理が徹底された場所での使用に適しています。 トレー形のケーブルラックを主に取り扱っているメーカーは、以下のとおりです。 トレー形のケーブルラックの取り扱いメーカー ネグロス電工...
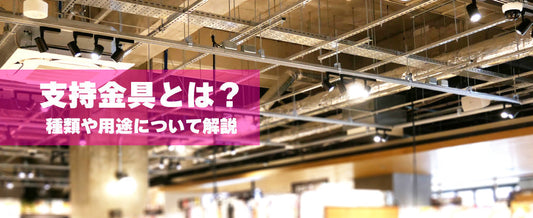
支持金具とは?種類や用途について解説
配管やケーブル、および重量物を建物へ安全に取り付ける際は、支持金具を使用します。支持金具を使用すると、建物へこれらの資材を頑丈に取り付けることが可能です。 ただし、支持金具は取り付け場所や吊り下げる物の種類によって最適な製品が異なるので、支持金具を使用する際は、各製品の特徴を把握しておきましょう。 そこで今回は、支持金具の基本情報や支持金具の種類を用途とともにご紹介します。 目次 支持金具とは 支持金具と用途 パイラック FVラック 吊り金具 振れ止め金具 支持金具とは 支持金具とは、配管やケーブル、重量物を支えたり、機器の落下を防止したりするために取り付ける金具です。 支持金具を取り付けると、建物にこれらの資材をしっかり固定できるだけでなく、地震や台風などが来てもズレにくくなります。 支持金具は使用場所や使用目的によって使い分けられるよう「パイラック」や「FVラック」「吊り金具」「振れ止め金具」など複数の種類があるため、それぞれの特徴を把握しておきましょう。 支持金具と用途 ここでは、支持金具の種類を用途とともに解説します。 パイラック パイラックとは、一般形鋼材に照明器具や吊りボルト、電線管を取り付ける際に使用する支持金具です。パイラックはネグロス電工の登録商標なので、他社では「Uラック」や吊りボルト支持金具」などと呼ばれています。また、パイラックは一般鋼材を挟み込むクリップ型の支持金具の総称として広く知られています。 パイラックは固定部分が波型になっているので、一般形鋼材に強く食い込みます。そのため、振動や衝撃だけでなく、引っ張られる力にも強いです。 パイラックの表面材質は電気亜鉛メッキが標準ですが、耐候性が求められる環境で使う場合は、オールステンレスや、溶融亜鉛メッキ処理がされたパイラックの使用がおすすめといえます。 パイラックを取り扱っている主なメーカーは、以下のとおりです。 ネグロス電工 バクマ工業 フェデポリマーブル 誠和 南電機 FVラック FVラックとは、一般形鋼に丸形ケーブルやVVFケーブルを挟み込んで固定するための支持金具です。 丸形ケーブルは通称「SVケーブル」とも呼ばれるケーブルで、屋内配線だけでなく、屋外や建物屋外側面へ取り付ける際に使用されます。また、VVFケーブルは通称「Fケーブル」とも呼ばれる低圧配電用ケーブルで、住宅など建物の屋内配線やクーラー配線で幅広く使用されています。 FVラックはドライバーの先端でクリップ部分をかんたんに広げられるので、丸形ケーブルやVVFケーブルが複数本あっても、ケーブルを傷めず挟み込むことが可能です。また、FVラックを一般形鋼に取り付ける際は、ドライバーの柄で押し込むだけで良いため、取り付けも手軽におこなえます。...
支持金具とは?種類や用途について解説
配管やケーブル、および重量物を建物へ安全に取り付ける際は、支持金具を使用します。支持金具を使用すると、建物へこれらの資材を頑丈に取り付けることが可能です。 ただし、支持金具は取り付け場所や吊り下げる物の種類によって最適な製品が異なるので、支持金具を使用する際は、各製品の特徴を把握しておきましょう。 そこで今回は、支持金具の基本情報や支持金具の種類を用途とともにご紹介します。 目次 支持金具とは 支持金具と用途 パイラック FVラック 吊り金具 振れ止め金具 支持金具とは 支持金具とは、配管やケーブル、重量物を支えたり、機器の落下を防止したりするために取り付ける金具です。 支持金具を取り付けると、建物にこれらの資材をしっかり固定できるだけでなく、地震や台風などが来てもズレにくくなります。 支持金具は使用場所や使用目的によって使い分けられるよう「パイラック」や「FVラック」「吊り金具」「振れ止め金具」など複数の種類があるため、それぞれの特徴を把握しておきましょう。 支持金具と用途 ここでは、支持金具の種類を用途とともに解説します。 パイラック パイラックとは、一般形鋼材に照明器具や吊りボルト、電線管を取り付ける際に使用する支持金具です。パイラックはネグロス電工の登録商標なので、他社では「Uラック」や吊りボルト支持金具」などと呼ばれています。また、パイラックは一般鋼材を挟み込むクリップ型の支持金具の総称として広く知られています。 パイラックは固定部分が波型になっているので、一般形鋼材に強く食い込みます。そのため、振動や衝撃だけでなく、引っ張られる力にも強いです。 パイラックの表面材質は電気亜鉛メッキが標準ですが、耐候性が求められる環境で使う場合は、オールステンレスや、溶融亜鉛メッキ処理がされたパイラックの使用がおすすめといえます。 パイラックを取り扱っている主なメーカーは、以下のとおりです。 ネグロス電工 バクマ工業 フェデポリマーブル 誠和 南電機 FVラック FVラックとは、一般形鋼に丸形ケーブルやVVFケーブルを挟み込んで固定するための支持金具です。 丸形ケーブルは通称「SVケーブル」とも呼ばれるケーブルで、屋内配線だけでなく、屋外や建物屋外側面へ取り付ける際に使用されます。また、VVFケーブルは通称「Fケーブル」とも呼ばれる低圧配電用ケーブルで、住宅など建物の屋内配線やクーラー配線で幅広く使用されています。 FVラックはドライバーの先端でクリップ部分をかんたんに広げられるので、丸形ケーブルやVVFケーブルが複数本あっても、ケーブルを傷めず挟み込むことが可能です。また、FVラックを一般形鋼に取り付ける際は、ドライバーの柄で押し込むだけで良いため、取り付けも手軽におこなえます。...

モールとは?種類や用途について解説
モールとは、電話線やLANケーブルなどの屋内配線を壁や床に固定したり保護したりするための配線資材です。モールを使用すると見た目も美しくなり、配線も傷付く心配がないので、屋内配線時はモールが使用されます。 ただし、モールには取り付け場所によっていくつか種類があるので、それぞれの違いを把握することが大切です。そこで今回は、モールの種類や用途を1つずつ解説します。 目次 モールとは モールの種類と用途途 マガリ エルボ デズミ イリズミ テープ付き モールとは モールとは、電話線やLANケーブルなど、さまざまな屋内配線を壁や床などに固定するための配線資材です。モールは配線をすっぽり覆うように取り付けるので、配線を保護したり、目立ちにくくさせたりする役割もあります。 モールは両面テープを使用して壁や床へ固定するため、施工時に接着剤やネジなどを使用する必要はありません。また、モールの形状は直線タイプだけでなく、カーブの付いた「マガリ」「テズミ」「イリズミ」などがあります。 モールの種類と用途 ここでは、モールの種類を用途とともにご紹介しましょう。 マガリ マガリとは、配線を水平方向に90度曲げたいときに使用するモールです。 直角配線は、ベースの直線モールを左右45度の角度でカットして連結させたり、ベースの直線モールの外側を片側のみ少しカットし、もう一方の直線モールを挿し込んで連結させたりしても施工できます。 しかし、配線はマガリを使わず床や壁に曲げて固定をすると、配線が傷付きやすく危険であるほか、施工しにくいです。一方、マガリを使えば配線を無理に曲げて固定したり、ベースの直線モールをカットしたりする手間をかける必要もなく、マガリの中へ配線を通すだけでゆるやかにカーブを付けられます。 配線は多くの場合、部屋の角に沿って這わせていくので、マガリは配線を美しく安全に這わせるために欠かせない配線資材といえます。 マガリを取り扱っている主なメーカーは、以下のとおりです。 マサル工業 エレコム フソー化成 ELPA エルボ エルボとは、カーブの付いたモールの総称です。そのため、先にご紹介したマガリもエルボの一種といえます。 エルボには、以下のように3つの種類があります。 エルボの種類 フラットエルボ(平面エルボ)...
モールとは?種類や用途について解説
モールとは、電話線やLANケーブルなどの屋内配線を壁や床に固定したり保護したりするための配線資材です。モールを使用すると見た目も美しくなり、配線も傷付く心配がないので、屋内配線時はモールが使用されます。 ただし、モールには取り付け場所によっていくつか種類があるので、それぞれの違いを把握することが大切です。そこで今回は、モールの種類や用途を1つずつ解説します。 目次 モールとは モールの種類と用途途 マガリ エルボ デズミ イリズミ テープ付き モールとは モールとは、電話線やLANケーブルなど、さまざまな屋内配線を壁や床などに固定するための配線資材です。モールは配線をすっぽり覆うように取り付けるので、配線を保護したり、目立ちにくくさせたりする役割もあります。 モールは両面テープを使用して壁や床へ固定するため、施工時に接着剤やネジなどを使用する必要はありません。また、モールの形状は直線タイプだけでなく、カーブの付いた「マガリ」「テズミ」「イリズミ」などがあります。 モールの種類と用途 ここでは、モールの種類を用途とともにご紹介しましょう。 マガリ マガリとは、配線を水平方向に90度曲げたいときに使用するモールです。 直角配線は、ベースの直線モールを左右45度の角度でカットして連結させたり、ベースの直線モールの外側を片側のみ少しカットし、もう一方の直線モールを挿し込んで連結させたりしても施工できます。 しかし、配線はマガリを使わず床や壁に曲げて固定をすると、配線が傷付きやすく危険であるほか、施工しにくいです。一方、マガリを使えば配線を無理に曲げて固定したり、ベースの直線モールをカットしたりする手間をかける必要もなく、マガリの中へ配線を通すだけでゆるやかにカーブを付けられます。 配線は多くの場合、部屋の角に沿って這わせていくので、マガリは配線を美しく安全に這わせるために欠かせない配線資材といえます。 マガリを取り扱っている主なメーカーは、以下のとおりです。 マサル工業 エレコム フソー化成 ELPA エルボ エルボとは、カーブの付いたモールの総称です。そのため、先にご紹介したマガリもエルボの一種といえます。 エルボには、以下のように3つの種類があります。 エルボの種類 フラットエルボ(平面エルボ)...

カップリングとは?種類や比較ポイントを紹介
電線管をつなげる際は、カップリングという配線資材を活用します。カップリングは電線管の長さを伸ばしたり、違う電線管同士を安全に接続したりする際に便利な配線資材なので、多くの現場で活用されています。 ただし、カップリングにはいくつか種類があるため、現場ごとにどのカップリングが適しているのか事前に把握しておくことが大切です。 そこで今回は、カップリングの概要や、種類別に用途をご紹介します。最後にカップリングの比較ポイントもご紹介するので、カップリング選びにお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。 目次 カップリングとは カップリングの種類・用途 カップリング ねじなしカップリング コンビネーションカップリング TSカップリング パイコン カップリングの交換時期の目安 カップリングの選び方・比較ポイント カップリングを扱う主なメーカー カップリングとは カップリングとは、電線管同士を接続する際に使用する配線資材です。カップリングはサイズの違う電線管や、鋼製電線管と合成樹脂電線管など、種類の違う電線管同士を接続する際にも使用されます。 カップリングは接続する電線管の種類に合わせ、ねじ付きタイプと、ねじなしタイプがあります。 カップリングを屋外で使用する際は、雨水や砂埃などが侵入して電線がショートしないように、事前に防水パッキンや袋ナットを使用した防水処理が必要です。 カップリングの種類・用途 ここからは、カップリングの種類を用途とともに解説します。 カップリング カップリングとは、内側がねじ切られているカップリングです。そのため、差し込む電線管も両端がねじ切られているものを使用します。 電線管を切断してカップリングにねじ込む際は、挿入部分が浅くならないように電線管へマークを付け、十分な深さを確保してから切断します。また、ねじ込む際は接続不良を防ぐために、切断した端部のバリを十分に除去する作業も必要です。 ねじなしカップリング ねじなしカップリングとは、カップリングの内部がねじ切られていないカップリングです。そのため、ねじなしカップリングは差し込む電線管もねじ切られていないタイプを使用します。 ねじなしカップリングは電線管を差し込んだだけでは抜け落ちてしまうので、カップリングに付いている固定ねじを締めて電線管を固定します。固定ねじは電線管に当たったら締めるのをやめるのではなく、完全にねじ切るまで締めることが重要です。 コンビネーションカップリング コンビネーションカップリングとは、種類が異なる電線管を接続する際に使用するカップリングです。具体的には、露出配線から埋設配線に変更したいときや、鋼製電線管を硬質ビニル管に変更したいときなどに使用します。 コンビネーションカップリングは、ねじなし電線管とねじ付き電線管だけでなく、合成樹脂可とう電線管(PF管)や硬貨ビニル電線管(VE管)、防水プリカなど、どのような電線管同士でも接続できるように豊富な種類で販売されています。 TSカップリング...
カップリングとは?種類や比較ポイントを紹介
電線管をつなげる際は、カップリングという配線資材を活用します。カップリングは電線管の長さを伸ばしたり、違う電線管同士を安全に接続したりする際に便利な配線資材なので、多くの現場で活用されています。 ただし、カップリングにはいくつか種類があるため、現場ごとにどのカップリングが適しているのか事前に把握しておくことが大切です。 そこで今回は、カップリングの概要や、種類別に用途をご紹介します。最後にカップリングの比較ポイントもご紹介するので、カップリング選びにお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。 目次 カップリングとは カップリングの種類・用途 カップリング ねじなしカップリング コンビネーションカップリング TSカップリング パイコン カップリングの交換時期の目安 カップリングの選び方・比較ポイント カップリングを扱う主なメーカー カップリングとは カップリングとは、電線管同士を接続する際に使用する配線資材です。カップリングはサイズの違う電線管や、鋼製電線管と合成樹脂電線管など、種類の違う電線管同士を接続する際にも使用されます。 カップリングは接続する電線管の種類に合わせ、ねじ付きタイプと、ねじなしタイプがあります。 カップリングを屋外で使用する際は、雨水や砂埃などが侵入して電線がショートしないように、事前に防水パッキンや袋ナットを使用した防水処理が必要です。 カップリングの種類・用途 ここからは、カップリングの種類を用途とともに解説します。 カップリング カップリングとは、内側がねじ切られているカップリングです。そのため、差し込む電線管も両端がねじ切られているものを使用します。 電線管を切断してカップリングにねじ込む際は、挿入部分が浅くならないように電線管へマークを付け、十分な深さを確保してから切断します。また、ねじ込む際は接続不良を防ぐために、切断した端部のバリを十分に除去する作業も必要です。 ねじなしカップリング ねじなしカップリングとは、カップリングの内部がねじ切られていないカップリングです。そのため、ねじなしカップリングは差し込む電線管もねじ切られていないタイプを使用します。 ねじなしカップリングは電線管を差し込んだだけでは抜け落ちてしまうので、カップリングに付いている固定ねじを締めて電線管を固定します。固定ねじは電線管に当たったら締めるのをやめるのではなく、完全にねじ切るまで締めることが重要です。 コンビネーションカップリング コンビネーションカップリングとは、種類が異なる電線管を接続する際に使用するカップリングです。具体的には、露出配線から埋設配線に変更したいときや、鋼製電線管を硬質ビニル管に変更したいときなどに使用します。 コンビネーションカップリングは、ねじなし電線管とねじ付き電線管だけでなく、合成樹脂可とう電線管(PF管)や硬貨ビニル電線管(VE管)、防水プリカなど、どのような電線管同士でも接続できるように豊富な種類で販売されています。 TSカップリング...