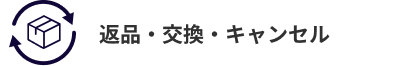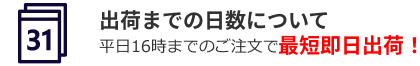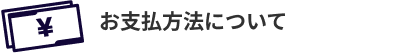ただし、VVFケーブルにはいくつか種類があるため、使用する際には用途別の使い分けが必要です。
そこで今回は、VVFケーブルの種類を用途別に解説していきます。VVFケーブルの選び方や比較ポイント、取り扱いメーカーもご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
VVFケーブルとは
VVFケーブルとは、一般住宅や商業施設など建物の屋内配線に使用される電線です。特に、15Aまでの照明やコンセント回路の電源供給用ケーブルとして活用されています。

シースは2芯が白・黒、3芯が白・黒・赤と色分けされているので、配線工事でのつなぎ間違いの防止に役立ちます。
VVFケーブルの種類・用途
ここでは、VVFケーブルの種類を用途別に紹介していきます。VA線
VA線はVVFケーブルの別称で、主に西日本で呼ばれていた名称です。VA線は「Vinyl Armored Cable」の頭文字を取って名付けられました。昭和39年3月にJIS規格が制定・改称されるまで西日本ではVVFケーブルのことをVA線、またはVAと呼んでいました。
VA線はVVFケーブルの呼び名が変わっただけなので、特徴や用途はVVFケーブルと同じです。
VA線のおすすめポイント
- 耐候性に優れている
- 芯が色分けされているため、配線工事でつなぎ間違いを起こしにくい
イチロクニシンFケーブル
イチロクニシンFケーブルとは、VVFケーブルの芯が1.6mmで、芯の数が2本のケーブルです。胴の心線をビニール樹脂で二重に覆っているため、天井などへの露出配線用としても活用できます。
また、芯がグレーや赤・黄色・青に色分けされているので、配線工事でつなぎ間違いを起こしにくい点も特徴です。
イチロクニシンFケーブルのおすすめポイント
- 天井などへの露出配線用にも使用できる
- 芯が色分けされているため、配線工事でつなぎ間違いを起こしにくい
エフ
エフとは、VVFケーブルの別称です。昭和39年3月にJIS規格が制定・改称されるまで、関西でVVFケーブルのことをVAケーブルと呼んでいたように、関東では「Falt」の頭文字からエフと呼んでいました。エフはVVFケーブルの呼び名が異なるだけなので、特徴や用途はVVFケーブルと変わりません。
エフのおすすめポイント
- 耐候性に優れている
- 芯が色分けされているため、配線工事でつなぎ間違いを起こしにくい
VVFケーブルの交換時期の目安
VVFケーブルの寿命は、屋内および許容電流を超えずに使用していれば、20年~30年といわれています。30年経過するとシースの劣化により絶縁が低下し、火災につながる恐れがあるので、VVFケーブルは20年~30年単位で点検・交換しましょう。
ただし、ケーブル内に水が入り込んだり、衝撃・圧縮・捻回などの外的要因やネズミやシロアリによる食害があったりすると、VVFケーブルの劣化が促進されるため寿命は短くなります。
VVFケーブルの選び方・比較ポイント

VVFケーブルの規格は、「芯数x太さ(mm)」のように表記されています。 一般的な太さは1.6mmと2.0mmで、1.6mmは照明など消費電力の小さい19A以下の家庭用コンセントに使用されるケースが多いです。
一方、2.0mmは20A以上の消費電力が大きいエアコンなどの配線に使用されるので、太さは接続する家電の消費電力に合わせて選ぶ必要があります。
また、芯の数は2本・3本・4本の3種類あり、芯数によって許容電流や外径が変わったりするため、芯数は接続先の電流や見た目の太さを基準に選びましょう。
VVFケーブルは多くのメーカーが同じ規格を発売していますが、皮膜の剥きやすさやケーブルの硬さなどは好みがあるので、レビューを比較しながらご自身に合ったものを選ぶのがおすすめです。
VVFケーブルを扱う主なメーカー
VVFケーブルを主に扱っているメーカーは、「矢崎エナジーシステム」「富士電線工業」「弥栄電線」「協和電線工業」「住電HSTケーブル」などです。
「矢崎エナジーシステム」は高熱・耐火性に優れている点、「富士電線工業」は安定と品質のコスパの良さが魅力のメーカーです。
「弥栄電線」は知名度・流通量の高さ、「協和電線工業」は細かいニーズに応えたVVFケーブルの取り扱いが豊富といった点が魅力といえます。
「住電HSTケーブル」は、一般住宅や商業施設などの低圧配線で大きなシェアを持っている点が特徴です。




























































































































 矢崎エナジーシステム
矢崎エナジーシステム

 弥栄電線
弥栄電線
 協和電線工業
協和電線工業
 住電HSTケーブル
住電HSTケーブル